
1月ってどんなマンスリー?
1年とは365日のこと。1年とは12ヶ月のこと。この記事では、後者のマンスリーにこだわって紹介していきたいと思います。「〇〇月ってこんな月」「〇〇月って毎年こんなことが起こる」など、月単位で物事を考えたり、季節を感じたり、目標を立てる方もいらっしゃるかと思います。では、いきましょう、今月ってどんなマンスリー?
さぁ、1年のはじまり。1月です
1月と言えば何を思い浮かべますか? お正月、年賀状、福袋、初詣、正月遊び、駅伝、餅つき、鏡餅、おせち料理、雑煮…がメジャーどころでしょう。また、1月の行事は、元日(1月1日)、書初め(1月2日)、七草がゆ(1月7日)、松の内(1月7日まで)、成人の日(1月第2月曜日)、小正月(1月15日)、初天神(1月25日)などがあります。始まりということでいろいろな想いを持って迎えられる人が多いと思います。勉強・学業、お仕事、趣味の習い事などに対して、気持ちを新たにする人もいらっしゃいますよね。ちなみに、1月1日のことを「元旦」や「元日」と呼んでいますが、元旦の「旦」は太陽が地平線から昇ってくるさま、つまり夜明けや朝という意味があります。ということは、元旦は1月1日の朝のことを指し、元日は1月1日の日中のことを指すということですね。はい、豆知識でございました。
では、1月を紐解いていきましょう
先ほど元旦と元日の違いをご紹介した1月1日(元日)は、1年の始めの日です。初日の出には、その年の幸運や豊作をもたらす年神様と一緒に現れるとされることから、拝むと縁起が良いと言われています。翌日、1月2日は「書初め」の日。書初めでは新年の豊富や祈願をしたためることが多く、書道の他にも稽古ごとをはじめるのに良い日とされています。1月7日は「人日の節句」。1年の健康と長寿を願って七草がゆをいただき、お正月にごちそうを食べすぎて疲れた胃を休めるという意味もあります。ちなみに元日から1月7日までを「松の内」と呼ぶそうです。ここまでをお正月とし、以降に門松やしめ縄などのお正月飾りを片付けることが習わしのようです。ただ、一般的には1月7日ですが、地域によっては1月15日までもあるそうです。
3学期はどんなイメージですか?
続いて、1月15日は1月1日の「大正月」に対して、「小正月」と呼ばれており、小正月にはその年のお正月飾りを燃やして天に返すどんど焼きの行事が行われたり、厄払いのために小豆粥を食べる地域もあります。どんど焼きは、他にもしめ縄や書き初めなどを、神社や広場に持ち寄って燃やすというもので、地域によって左義長(さぎちょう)や「道祖神祭」とも呼ばれているそうです。どんな意味合いがあるyかと言うと、お正月に家に来てくださった神様を立ち上る煙とともに見送る、とし、1年の無病息災や商売繁盛などを祈る行事なのです。…とは言え、お子さんにしてみれば冬の楽しみイベントがひと段落し、寒さが厳しくなるだけと思っているかもしれませんね。新年は改めてスタートを切るタイミング、何かを始めてみたり、改良・改善を心に秘めてさらなる成長を目指して日々元気に過ごしていきましょう。

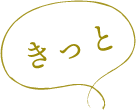 あなたにピッタリな記事
あなたにピッタリな記事




